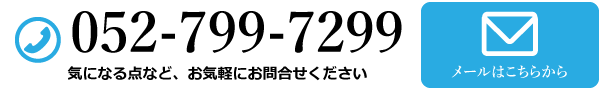寒さが本格化してくると、エアコン業界において“普通の夏”“春秋”とは違ったトラブルが飛び交うようになります。私たち業者にとって、それは単なる故障対応だけでなく、事前の備えや対策こそが他社と差をつけるチャンスでもあります。この機会に、冬季に急増する代表的なトラブルと、その現場対応力を高める方法を整理しておきましょう。
冬季に急増するトラブル傾向 ―― 事故になる前の“水・凍結・霜”の三重苦
業者として特に意識すべきなのは、見落とされがちな「水」と「氷」に関わるトラブルです。暖房を使うことで発生する霜取り運転、排水経路の凍結、室外機周辺の雪・氷付着が三重に絡みあって、複雑なトラブルを生みます。
まず、暖房運転時に室外機に霜がつくと、エアコンは自動で「霜取り運転(デフロスト)」を開始します。この際、暖房が一時停止し、室外機が自己加熱して霜を溶かします。これ自体は異常ではないものの、この過程で大量の水が発生します。そしてこの水がスムーズに排出されなければ、室内機や配管、天井裏などで水漏れを引き起こすことがあります。
さらに、溶けた水が屋外で再び凍結することで、ドレン管自体が塞がれたり、排水口が氷で閉塞されたりします。また、室外機に雪や氷が付着して、吸気・排気の流れを阻害することも頻繁に起こります。これらが重なり合うことで、普通の故障対応では収まりきらない複合症例が現場で増えていくわけです。
業者が押さえるべき現場チェックポイントと優先順位
現場に入った際、まずチェックすべきポイントを順序立てて頭に入れておくことが、対応スピードと信頼度を左右します。
- ドレン系の排水確認
室外機ドレン排出口、出口付近の雪・氷・土・ゴミなどをまず確認。詰まりや凍結があるなら、排水確保を最優先で。 - 室外機周囲の除雪と空間確保
室外機の前後左右 30〜50cm は必ず風通しを確保。雪で埋もれている場合は丁寧に除雪、付着した氷があれば慎重に除去。 - 霜取り運転の様子を確認
お客様から「暖房が効かない」との訴えがあった場合、まずは霜取りの動作タイミングが正しいかをチェック。停止時間が長すぎたり頻繁すぎたりするようなら、センサー誤差や冷媒不足、汚れの可能性を疑う。 - フィルター・熱交換器の状態確認
汚れの蓄積があると暖房効率を著しく落とす。内部が汚れていると、霜取り運転の頻度が増えてしまう傾向も。 - 冷媒量・配管状態の点検
古い機器では冷媒の微漏れが起きやすく、冬場の暖房効率低下要因となる。配管の断熱不良や劣化も要チェック。 - エラーコード・保護回路異常の確認
エラー表示が出ているなら、センサー異常、低圧保護、高圧保護、凍結保護などの信号を読み取り対処。
これらを順序よく確認していくことで、現場での時間ロスを抑えつつ信頼性を確保できます。
対応策・補強策(業者として提案すべき技術と材料)
ただ「直す」だけでなく、「再発を防ぐ」提案ができるかどうかが勝負。以下のような補強策を現場で持ち合わせておくと、契約率アップにもつながります。
- ドレンヒーター/保温材設置
ドレン管や室外機近辺の配管にヒーター線を入れて凍結を防ぐ。特に寒冷地や標高の高い地域では効果が高い。 - 防雪フード・室外機カバー
直雪・吹き込み雪を防ぐカバーや風除けフードを設置しておくと、雪害を軽減できる。 - 高置設置(台上設置)
積雪リスクを下げるため、室外機を地面からかさ上げする設置を提案することも有効。 - 配管断熱材の見直し
特に配管長が長い物件では、断熱材の劣化が熱ロスを招き、霜取り頻度を高める要因になることも。 - 暖房効率改善への内部洗浄・クリーニング提案
熱交換器や内部配管の汚れ除去やスケール・スラッジ除去を行うことで、冬の暖房能力を復元できることも多い。
これらの提案を標準オプションとして準備しておけば、現場で差別化できるし、お客様にも安心感を持ってもらえる。
日本空調のブログページに訪問して頂き誠に有難うございます。
また最後までブログを読んで頂き誠に有難うございます。
弊社はお客様をはじめ、取引先様の皆様や協力業者の皆様、そしてそのご家族、日本空調に関わって頂ける全ての人々に喜んで頂きたい、また満足して頂きたいという想いから設立致しました。
今後もエアコン工事という分野で、社会に大きく貢献し皆様に喜びや感動を与えられる
企業で在り続けるため、誠心誠意努めて参ります。
ぜひ全国のエアコン工事協力業者様からのお問合せをお待ちしております。
TEL:052-799-7299
MAIL:info@nihonku-chou.co.jp